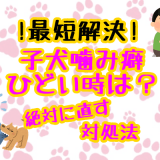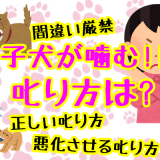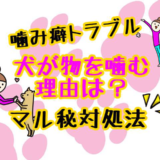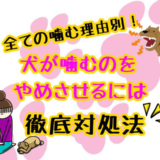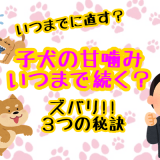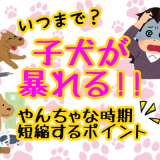エリちゃん
エリちゃん
 わんこ先生
わんこ先生
子犬が人の足を噛む理由とは?

子犬の頃は、好奇心から何かを調べたいと思うとにおいを嗅いだり噛んだりしてそれがどういうものなのかを調べていきます。
また、子犬は飼い主さんとのコミュニケーションをとりたい時や、飼い主さんへの愛情表現にも噛むという行動をとります。
さらに生後7か月頃までの歯の抜け変わり期の口の中に感じる違和感を紛らわせたいという思いから、なんでも噛みたいと思う気持ちが強いです。
ですから、子犬の時期は飼い主さんなどの人の事も噛みやすいですし、家具やソファーの足なども噛んでしまいやすく、家をボロボロにされるとお悩みの飼い主さんも多いです。
 子犬が人や物を噛むというのは、悪いことをしているわけではなく、ごく自然な行動ではあるんですが、だからと言ってそのまま噛むことを許してしまうとひどい噛み癖に繋がったり、人を平気で噛んでしまう犬に育ててしまいますから、ちゃんと対策をとる必要があります。
子犬が人や物を噛むというのは、悪いことをしているわけではなく、ごく自然な行動ではあるんですが、だからと言ってそのまま噛むことを許してしまうとひどい噛み癖に繋がったり、人を平気で噛んでしまう犬に育ててしまいますから、ちゃんと対策をとる必要があります。
その中でも今回は、まずは飼い主さんなど人の足を集中して噛む場合の子犬についてその理由を理解して、しっかりと対策をとる方法をご紹介していきます。
後半では、子犬が人の足ではなくて自分の足を噛む場合の理由と対策についてもご紹介していこうと思います。
子犬が自分の足を噛んでいる場合、おとなしいからいいやと放っておくと、子犬の体や心に大きなダメージを追わせてしまう可能性もありますので、こちらもしっかりと対策していきましょう。
まず子犬が飼い主さんなど人の足を噛む理由ですが
- 噛みやすい位置にある
- においが気になる
- 動くものが気になる
- 恐怖や自己防衛のため
- 抵抗や威嚇のため
という5つの理由がありますが、その前に子犬を正しく飼えていないという恐れがあります。
正しく飼えていないというのは、子犬の生活パターンが乱れていたり、子犬という動物を理解できていないことから間違えた対応をしていたり、必要なしつけを始められていないということです。
子犬が人の足を噛むことと関係がないことに思えるかもしれませんが、子犬の行動をこれから正しく導いていってあげる必要があるのに、飼い主さんに必要な知識がないというのは大問題です。
子犬が人の足を噛むのは子犬なりの理由はありますが、正しい行動とは言えません。
子犬の間違えている行動を正しい行動に導いていく・新しく人間社会のルールで正しい行動を教えていく(しつけ)にあたって、飼い主さんが何も知らないのでは、いきなり車を運転するようなものでそのうち大事故を起こします。
すでにトイレのしつけは始められていらっしゃると思いますが、もうトイレはできるようになりましたか?
トイレ以外のしつけも始められていらっしゃるでしょうか?
まだトイレが完璧ではないとか、特にしつけを始めていないとか、イマイチどんなしつけをどうやってしたらいいのかわからないという方もいらっしゃると思います。
特に子犬が飼い主さんなど人の足を噛むといった行動をとっているのなら、すぐに適切なしつけをしていく必要があります。
適切なしつけと言っても、子犬に厳しく接したり、警察犬の訓練のようなことをするわけではありませんので安心してください(^^)
子犬へのしつけは正しい主従関係を築くためのトレーニングを行っていくことなんですが、この「主従関係」という言葉は間違った認識で使われたり、誤解を招きやすいので「信頼関係」という言葉を使っていきます。
まだ赤ちゃんである子犬と信頼関係が築けるのか疑問を抱かれるかもしれませんが、子犬は非常に成長が早いので生後4か月には信頼関係を築くことができるまで成長しています。
本来は、基礎的な子犬のしつけは生後6ヵ月くらいまでに終わらせて、生後8か月くらいまでにはほとんどの基本的なしつけが終わっていることが望ましい状態です。
そうじゃないと、子犬に遊び噛みや要求噛みなどが見られてくるので、足だけじゃなく色々なところを噛まれるようになったり、やんちゃすぎて手に負えない子犬にしてしまう危険がかなり高くなります。
子犬の噛みをひどくしない・やんちゃにしないためには、子犬に正しい方法で正しいしつけをしてあげる必要があるんですね。
正しい子犬のしつけ方法というのはどんなものなのか?というと、非常に広範囲にわたるものになるので、私が子犬のしつけにお悩みの方からご相談を受けたときは、いつもイヌバーシティというしつけの方法をまとめた教材をおすすめしています。
人の足を噛む子犬というのは、今のままにしておくと噛み癖に繋がる恐れのある危険な状態です。
正しい行動を子犬にわかりやすく教えてあげられないと、子犬は正しい行動を学ぶことができません。
ここで良くやる方法がネットで調べるという方法だと思いますが、ネットで調べる方法だと例えば「人の足を噛む時の対処法」だけは知れるかもしれませんが、しつけをトータルで知ることができません。
しかも、現在は一昔前の「犬には上下関係を教える」という考え方のしつけがまだかなり多く残っているので、ネット上のしつけを調べているとあまり望ましくない方法もたくさんあるのが現状です。
望ましくないしつけ方法や考え方と望ましいしつけを混ぜて子犬に教えてしまうと、子犬も混乱して正しい方法が伝わらないため、「教えているのにできない」「いつまでたっても正しい行動ができない」ようになり、しつけに時間がかかったり子犬をできない犬と誤解してしまうことに繋がります。
さらにこれから出てくる子犬の困った行動に対しても、なかなか直らないことに繋がり、人の足を噛むことをやめさせることだって難しいことになってしまいます。
ネットで独学のしつけを行うということは多くのデメリットがあるということを知っておいていただきたいと思います。
その点、イヌバーシティはこれ一つあればこれから子犬をしつけるにあたって必要な知識や必要な考え方、必要なトレーニング方法など、飼い主さんに必要なことが網羅されています。
特に飼い主さん目線で考えられて作られているので、飼い主さんがつまづきそうな部分や、やりにくいと感じそうな部分も徹底してわかりやすく解説されています。
しつけ教室に通っていただくのも良いのですが、金額が高額になる割にお利口さんな犬に育てられたというお話を聞くことが少なく、犬に対する知識が増えたということもあまり聞きません。
イヌバーシティなら、わかりやすい実戦形式の動画のほかに、子犬を育てるために飼い主さんが知っておかないといけない知識も講習という形で網羅されているので、気がつけば子犬にとって良い飼い主になることができるという大きなメリットがあります。
とはいえ、いきなりお勧めされても本当に必要なものなのかご判断を迷われると思います。
「イヌバーシティって良さそうだけど…うちの子に必要なのかな?」と、少しでもイヌバーシティにご興味を持っていただけたら、実際に実践した飼い主さんからいただいた感想や、実践するメリットをご紹介している記事がありますので、一度ご覧になってみてください。
 関連記事
関連記事
ウソみたいにお利口さんになる特別な秘訣を大公開です!
ちょっと強力過ぎじゃない!?見違えるほどお利口になるしつけ方法があるの?
子犬のしつけの重要性や正しいしつけ方法があるということについて分かっていただいたところで、子犬が人の足を噛む5つの理由についてそれぞれ詳しく見ていきたいと思います。
人の足を噛むのは噛みやすい位置にあるから
 小さい子犬にとって、一番近くで噛みやすいのが人の足です。
小さい子犬にとって、一番近くで噛みやすいのが人の足です。
足は子犬にとって噛みやすい位置にあるものなので、子犬が噛む機会が多くなってしまうというのが子犬が足を噛む理由の1つです。
例えば、吠えても飼い主さんの行動が変わらないときは、さらに激しい「噛む」というアクションをとろうとしますが、その時に子犬が噛めるのが「人の足」です。
このように飼い主さんに何らかの要求がある場合などに足を噛むことがありますが、他にも飼い主さんにかまってほしい・飼い主さんの関心を引きたいという気持ちからも飼い主さんの足を噛むことがあります。
手を噛む時は、比較的遊びの気持ちが強い場合が多いですが、足を噛む時は子犬の気持ちを伝えるためということが考えられます。
人の足を噛むのはにおいが気になるから
 子犬は飼い主さんのにおいが大好きな子が多いです。
子犬は飼い主さんのにおいが大好きな子が多いです。
人間よりもにおいからの情報が大切な犬にとっては、とてもにおいに敏感で、特に大好きな人のにおいに対しては「欲しい」「自分のものにしたい」という気持ちが働きます。
だから、洗濯物が触れるような状況にあると、大好きなにおいがする洗濯物を自分のものとして隠すなど、私たちからしたらいたずらと思えるような行動をとるんですね。
飼い主さんが靴下を履いていたり、スリッパを履いていると、その靴下やスリッパを手に入れたいと思って噛みついたら飼い主さんの足も一緒に噛んでしまうということも考えられます。
人の足を噛むのは動くものが気になるから
 犬には動くものを追うという習性がありますが、子犬にもその習性があります。
犬には動くものを追うという習性がありますが、子犬にもその習性があります。
特に遊び好きな子犬にとっては、遊びの一環としても動くものを追いたくなりますが、人間の足は目の前の動くものとして子犬に認識されやすいという点があります。
また、長いスカートをはいていたり、長いズボンをはいている場合は、裾がヒラヒラしているように見えて、裾の部分が気になって噛みつこうとします。
勢い余って裾ではなく足を噛むことになる場合も少なくありません。
人の足を噛むのは恐怖や自己防衛のため
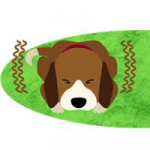 これはあまり無いことを祈りますが、子犬を蹴ったことがある場合などは、子犬にとって人間の足が恐怖の対象になってしまうので、足が近づいてくると先に攻撃をしようとして噛むことがあります。
これはあまり無いことを祈りますが、子犬を蹴ったことがある場合などは、子犬にとって人間の足が恐怖の対象になってしまうので、足が近づいてくると先に攻撃をしようとして噛むことがあります。
故意に蹴ったわけではないけど、結果的に蹴った形になってしまった場合や、悪気はないんだけどしっぽを踏んでしまったとか、足を踏んでしまって子犬に痛い思いをさせてしまうこともこれに当たります。
子犬は痛みや怖いと思ったことに対して強い恐怖を抱くようになるので、トラウマとして心に残り、恐怖を感じた対象から身を守ろうとして先に噛むという攻撃行動を起こしやすくなります。
人の足を噛むのは抵抗や威嚇のため
 子犬の時は、成犬よりも色々なことに慣れるのが早いですが、まだ慣れていないのに急に嫌だと思うことをされるとやはり抵抗をしようとします。
子犬の時は、成犬よりも色々なことに慣れるのが早いですが、まだ慣れていないのに急に嫌だと思うことをされるとやはり抵抗をしようとします。
一度、ケアなどを嫌だと思ってしまうと、そのケアを飼い主さんがしようとするとそれを察して抵抗のために威嚇をしようとして噛むことがあります。
この場合は、基本的にはあまり強い噛み方ではないことが多いですが、飼い主さんの足を噛む対象として狙った場合は思いのほか強く噛んでしまいがちです。
子犬に対するケアなどは、徐々に慣らしていくことを心がけてもらうといいでしょう。
子犬が足を含む人を噛む時の対処法

何度も申し上げていますが、子犬に悪意がなかったとしても足を含む人を噛むという行動は直してあげないと飼い主さんにとっても子犬にとってもストレスになる可能性が高いです。
足だって噛まれれば痛いですし、飼い犬に噛まれるということは飼い主さんに痛みとともに精神的ショックを与えることもありますし、恐怖を感じさせてしまう恐れもあります。
子犬が私たち人間の足や、それ以外の場所も含めて「噛む」ことをやめさせるための対処法をご紹介していきたいと思います。
人を噛まないために信頼関係を築く
 こちらは先ほどの子犬に正しいしつけをすることを徹底するということをすこし掘り下げたものになります。
こちらは先ほどの子犬に正しいしつけをすることを徹底するということをすこし掘り下げたものになります。
最初の方でも申し上げましたが、今までは犬には上下関係を教えて人が犬よりも上の順位にいるからリーダーなんだと分からせるという考え方のしつけでした。
この考え方の元でしつけを行ってきたので、
- 犬へのご飯は一番最後にしないといけない
- 子犬でも厳しく接しなければいけない
- 悪いことをしたら仰向けにして抑えつける
- 噛まれたら噛み返すくらいの気持ちでしつける
というしつけを推奨している訓練士がいまだにいらっしゃいますし、ネットでも勧めている飼い主さんがたくさんいらっしゃいます。
ただ犬への研究も理解も深まってきている現代、歯科も犬と同じ室内で飼うことを推奨している今において、このような上下関係を教えるしつけをしていては犬も飼い主さんもストレスになります。
確かに外で番犬代わりに犬を飼うというのが主流だった昭和初期などは上下関係を教えるしつけが行われていましたが、現在は世界的に見ても犬とは信頼関係を築くという考え方のしつけがスタンダードです。
今までは、犬は家族全員に順位をつけていると言われてきましたが、実はその家族との信頼関係によって態度が変わっているといわれるようになっています。
上下関係を教えるしつけには、痛い思いをさせたり驚かせたりといったしつけ方法が含まれていましたので、犬の恐怖の感情を利用したしつけをしていたんですね。
でも、信頼関係を築くという考え方のしつけは、犬に「安心して頼って良い人を教える」方法のため、犬にも飼い主さんにも全くストレスなく楽しい気持ちのまましつけをするしつけになっています。
犬も安心して頼って良い人に対して「大好き」という感情が芽生えるため、好きな人が喜んでくれる行動・好きな人が望む行動をとって褒めてもらおうと考えるわけです。
大好きな主人の指示だから喜んで従いたいと思う関係が正しい主従関係です。
イヌバーシティでは、この信頼関係を築く理想的な主従関係になるためのしつけ方法なので、子犬も飼い主さんもストレスを感じることなく、短期間でしつけをスムーズに行うことができるというのもおすすめしたい大きなポイントです。
いくら良いと勧められても「イヌバーシティってうちの子に必要なのかな?」と思われるでしょうし、そもそもイヌバーシティを実践するメリットがいまいち感じられないかもしれません。
そのような方に、イヌバーシティを実際に実践した飼い主さんからいただいた感想やどのように愛犬が変わったのか、実践する数々のメリットをご紹介していますのでここをタップしてその記事を、一度ご覧になってみてください。
犬に対するしつけというのは、子犬も含めて「そのトレーニングができるようになったら終わり」ということではなく、成犬になっても継続して行うものです。
正しいトレーニングをしていれば、子犬でも成犬でもその時の犬の気分次第でできたりできなかったりすることなく、飼い主さんからのコマンドにいつでも従いたいという気持ちにすることができます。
それだけでなく、犬は自分で考えて飼い主さんが喜ぶ行動をとりたい!と思うようになるんですね。
こうなれば、犬は飼い主さんや家族などの足はおろかどこも噛みたいという気持ちにはなりませんから、犬の噛み問題に悩むということはなくなります。
この状態が完全にしつけの入った犬ということになりますが、これは訓練士さんなどのプロでなくてもできることです。
間違えたしつけで犬を混乱させないためにも、子犬のうちからイヌバーシティを知ることで正しく最短でしつけられて信頼関係が築けるしつけの方法というのを行っていただきたいと思います。
しっかりと遊ぶ時間を作る
 犬が噛むという行動もそうですが、犬が問題行動を起こす原因になるのが飼い主さんからの愛情不足や運動不足、睡眠不足です。
犬が噛むという行動もそうですが、犬が問題行動を起こす原因になるのが飼い主さんからの愛情不足や運動不足、睡眠不足です。
愛情や運動、睡眠が不足してしまうと、犬はストレスを感じやすくなりストレスがたまってしまうことで問題行動を起こしやすくなります。
犬としっかりと遊ぶ時間を作ることで、子犬は飼い主さんとの時間を楽しみ心が満たされるだけじゃなく、体を使って運動もできますし、運動をするからこそしっかりと眠ることができます。
何となくケージから出して好きに遊ばせてあげる時間を多く取るよりも、そんなに長くはない時間だけど飼い主さんがしっかりと子犬が満足できるような遊びをしてあげることが大切です。
犬と遊ぶことは子犬を育てる上でも非常に重要なことなんですが、おろそかに考えてしまう飼い主さんが多いのがもったいないことだと思います。
イヌバーシティでは遊ぶことの重要性から、犬との遊び方だけで1つのコンテンツを用意しています。
そもそもどうやって犬と遊べばよいのか?効率の良い遊び方などをまだご存知ないのでしたら、イヌバーシティはとてもお役に立てると思います。
子犬が人の足などを噛む場合には、子犬との遊びを見直し十分な遊び時間を作ってあげられているかを見直してみるのも効果的です。
禁止用語でいけないことを伝える
 信頼関係が築けている犬に対しては、「ダメ」とか「いけない」といった禁止用語で、その行動をしてはいけないと伝えることができます。
信頼関係が築けている犬に対しては、「ダメ」とか「いけない」といった禁止用語で、その行動をしてはいけないと伝えることができます。
ただ、注意していただきたいのが、禁止用語でいけないことが伝えられるのは、飼い主さんのことが大好きで信頼できる関係であることが前提なんですね。
先ほどの信頼関係を築く項目でも触れましたが、犬が飼い主さんを信頼し、大好きだからこそ飼い主さんがいけないということをやめようと思います。
犬は基本的に、してほしい行動を褒めることでその行動が定着していくので褒めることが有効なんでが、私たちはつい、禁止用語を連発して「してはいけないこと」を禁止することで正しい行動を教えようとしがちです。
でも犬を禁止用語でしつけることは非常に難しく、こちらが意図したことが伝わらないことが多いです。
例えば、犬が粗相をしたときに「ダメ」と叱ると、犬は排泄をすること自体がいけないことだと受け取ってしまって、排泄を我慢してしまうこともあります。
このように、犬に勘違いをさせないためにも、子犬のうちから信頼関係を築いて禁止用語が伝わるように正しくしつけをする必要があります。
禁止用語が伝わるようになれば、人の足を噛もうとしたときに「ダメ」などで噛む行動を制限することができるようになります。
噛んでも良い丈夫なおもちゃを与える
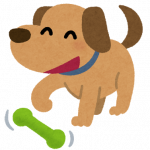 犬はそもそも噛みたいという欲求を本能レベルで持っている動物です。
犬はそもそも噛みたいという欲求を本能レベルで持っている動物です。
ですから、噛みたいという欲求は満たしてあげないと、それも犬にとってストレスになってしまうので、一緒に遊ぶおもちゃとは別に噛んでも良いおもちゃを与えてあげて噛む欲求を満たしてあげることが効果的です。
この時のおもちゃは、ぬいぐるみなどの柔らかいおもちゃだと壊してしまって中の綿などを誤飲してしまう可能性があるので、できるだけ丈夫で壊れる危険の少ないおもちゃを選ぶようにしてください。
歯磨きももちろん毎日のケアとしてする必要がありますが、噛むことで歯磨き効果も期待できるロープやガムもありますのでおすすめです。
犬もいつも同じおもちゃだと飽きて見向きもしなくなってしまうので、いくつか種類を用意してローテーションするなど飽きさせない工夫もしていきましょう。
犬は自分が好きなおもちゃじゃないと遊ばないこともあり、けっこう好みを持っています。
愛犬の好きなおもちゃを見つけてあげるように、子犬の頃はいろいろなおもちゃで遊んで、愛犬の好みを知るようにしましょう。
 エリちゃん
エリちゃん
 わんこ先生
わんこ先生
子犬が自分の足を噛む理由とは?

子犬が大人しいなと思ったら自分の足をしきりに噛んでいる様子を目にすることがあるかもしれません。
犬が自分の体を舐めるグルーミングとは別に、明らかに自分の足を噛んでいる姿を見たらどうしたのか心配になるでしょう。
この時、数分足を噛んでいたけど、飼い主さんに気付いたらすぐにやめて遊びたそうに振る舞っていたら、暇を持て余して自分の足を噛んでいたことが考えられます。
噛むという刺激が思ったよりここちよくて、癖になってしまう子犬もいますが、飼い主さんとすぐに遊びたがったり、元気な様子だったら特に問題はありません。
ただ、しつこく自分の足を噛み続けていたり、あまり元気がないような場合は他の理由が考えられます。
考えられる理由としては
- 痛みやかゆみがある
- しびれがある
- 関節や皮膚に違和感がある
- 気持ちを落ち着けたいというボディランゲージ
- ストレスからくる常同行動
このような理由で自分の足を噛み続けている恐れがあるので、子犬が自分の足を噛んでいる場合は子犬の様子を注意深く観察してください。
子犬が自分の足を噛むのは痛みやかゆみがあるから
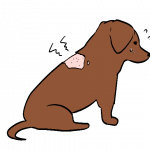 子犬がしきりに噛んでいる足や周辺などに痛みやかゆみがあることが考えられます。
子犬がしきりに噛んでいる足や周辺などに痛みやかゆみがあることが考えられます。
大きな外傷ならすぐにわかりますが、被毛に覆われているので小さな外傷はすぐに気づけないこともありますし、皮膚が炎症している皮膚炎や指の間に炎症が起きてしまう指間炎などは発見することがむずかしいです。
また外からは見えない関節炎や捻挫などで痛みを感じている可能性もあります。
アレルギーを起こしていたり、寄生虫に寄生されてしまった時は強いかゆみを伴うので、気になって患部を噛む行動が増えますし、中にはシャンプーが体質に合わなくて部分的にかゆみが出るということもあります。
怖い病気になると、関節に腫瘍ができてしまったときなども足を噛む行動が見られます。
子犬が自分の足を噛むのはしびれがあるから
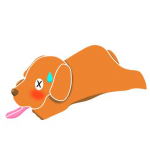 痛みやかゆみではないけど、しびれている感覚があるとやはり違和感から患部を噛む動作をします。
痛みやかゆみではないけど、しびれている感覚があるとやはり違和感から患部を噛む動作をします。
しびれが起こるのは、ヘルニアなど脊髄や神経が損傷していることが考えられます。
ダックスフントやコーギーといった胴長の犬種が椎間板ヘルニアになりやすいことはご存知だと思いますが、パグなどの肥満になりやすい犬種や、体重の重い大型犬も椎間板ヘルニアを起こしやすいです。
子犬が自分の足を噛むのは関節や皮膚に違和感があるから
 関節や皮膚の部分に痛みやかゆみとして症状が出る病気もありますが、他の病気の初期状態で、何となく違和感を感じることがあると足を噛むことがあります。
関節や皮膚の部分に痛みやかゆみとして症状が出る病気もありますが、他の病気の初期状態で、何となく違和感を感じることがあると足を噛むことがあります。
この場合は、はっきりとした症状が出ていないので、見た目などでは判断することがむずかしいかもしれません。
数日前までさかのぼって子犬の元気具合や、いつもと変わったことがなかったか、尿や便の様子に変わりはなかったかを思い出して、いつもと様子が違うことがなかったか振り返ってみてください。
子犬が自分の足を噛むのは気持ちを落ち着けたいというボディランゲージ
 犬は自分の気持ちを言葉で表現できないので仕草で表現しています。
犬は自分の気持ちを言葉で表現できないので仕草で表現しています。
子犬がしきりに自分の足を噛む時は、自分の気持ちを落ち着けたいと思っている可能性もあります。
例えば、家族団らん中に、自分だけケージの中にいて家族から離れているときや、来客中で飼い主さんがお客さんと夢中で話しているときなど、自分もかまってほしいという気持ちを落ち着けるために足を噛みます。
その他、犬はとても平和主義な動物なので、家族がケンカをしているときとか、誰かが怒られているときなども不安になり足を噛み続けることがあります。
子犬が自分の足を噛むのはストレスからくる常同行動
 犬は激しいストレスを感じると意味のない同じことを繰り返す行動をとることがあります。(常同行動)
犬は激しいストレスを感じると意味のない同じことを繰り返す行動をとることがあります。(常同行動)
例えば、分離不安の犬が1人でお留守番をしているときなどに、体の一部分を舐め続けたり、足を噛み続けるといった常同行動が見られることもあります。
頻繁に常同行動が見られる場合は、犬に強いストレスがかかっていて、心の病気になっている可能性を考える必要があります。
<犬も仮病をするの!?>
 犬は非常に賢い動物で、大切にされたことは長く記憶に残っています。
犬は非常に賢い動物で、大切にされたことは長く記憶に残っています。
過去にケガをして大切にされたことがあるとそれを覚えていて、痛いフリをして足を引きずるように歩くことがあります。
飼い主さんが仕事で忙しいとか、新しい家族が増えたときなど、飼い主さんの愛情がほかに向いていると思ったときなどに、飼い主さんに振り向いてほしい一心で取る行動です。
発見した時は、仮病を疑わずに病院に連れていかないといけませんが、もしなんでもなかった場合は仮病を叱らずに愛情を示してあげて安心させてあげてください。
子犬が自分の足を噛む時の対処法

子犬が自分の足を噛む時は、体や心の異常をまずは疑ってみてください。確認したいポイントは
- 被毛をかき分けて状態を確認する
- 他の症状がないか観察する
- 環境に変わりはないか見直す
- 睡眠・愛情・運動が不足していないか見直す
まず被毛をかき分けて皮膚の状態を確認します。
皮膚に発疹はないか、赤や黒く変色しているところは無いか、フケなどが出ていないか、被毛のツヤが悪くなっていないかなどを念入りに見ていきます。
噛んでいる足の部分に症状が出ているとは限らないので、周辺部をくまなく見てみるようにしてください。
病気などになっている場合は、噛むほかに症状が出ていることが多いです。
普段から愛犬の平熱を知っておくことは健康を管理するうえで大切なことなので熱が出ていないか測っておくと良いでしょう。
体調が悪い時は、尿や便に症状があらわれることも多いので、健康な状態の尿や便か?嘔吐などは無いか?も確認しておいてください。
環境の変化についてですが、犬は子犬でも環境の変化に対してストレスを感じやすいです。
 引越しをしたといった大規模な環境の変化だとわかりやすいですが、近くで道路工事が始まったとか、近くで家を建て始めたなどで、騒音が始まった場合なども子犬にとっては環境の変化になります。
引越しをしたといった大規模な環境の変化だとわかりやすいですが、近くで道路工事が始まったとか、近くで家を建て始めたなどで、騒音が始まった場合なども子犬にとっては環境の変化になります。
特に、人間よりも音を大きく聞こえてしまう犬にとっては、断続的に続く音や金属音などは想像を超える苦痛になることがあります。
短期間で終わるものなら仕方ないですが、長期に及ぶようだったら窓に防音カーテンをつけるといった対策をしてあげたほうが良い場合もあります。
あと、今まではマンションなどの高層階に住んでいたけど、一戸建てに引っ越した場合などは人間も外の音の大きさに驚くかもしれませんが子犬も同じです。
子犬が早くなれるようなら良いのですが、いつまでも情緒不安定な様子ならやはり防音カーテンなどで対策をする必要があるかもしれません。
先ほども述べましたが、犬が強いストレスを感じてしまう大きな原因が、睡眠・愛情・運動の不足です。
特に睡眠に関しては、慢性的に睡眠時間の子犬がとても増えている傾向にあります。
子犬の生活パターンを整えてあげるのも大切な飼い主さんの務めですので、子犬が十分に良質な眠りがとれているのか見直してみてください。
子犬の生活パターンや、犬との遊び方、犬との接し方というのも、しつけのトレーニングとは別にイヌバーシティで詳しく解説されています。
こういう部分は、本などにもあまり書かれていない部分なので、子犬のうちに知ることは大きなメリットになると思います。
あと、少数かもしれませんが空腹である可能性というのもあるんですね。
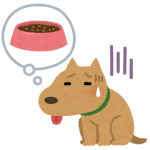 だいたい子犬は生後6か月くらいまでは一日に3回、それ以上になったら一日に2回に分けてご飯を上げていると思いますが、子犬によっては1回に十分な量を食べられていなくて空腹になってしまっていることもあります。
だいたい子犬は生後6か月くらいまでは一日に3回、それ以上になったら一日に2回に分けてご飯を上げていると思いますが、子犬によっては1回に十分な量を食べられていなくて空腹になってしまっていることもあります。
もともと食欲が旺盛の子犬もいます。
子犬の様子を見て、1回分を少なくして回数を増やしたり、低カロリーのトッピングを乗せてあげるなど子犬に合わせて食餌を調節してみてください。
たまに、子犬が足を噛む時の対処法として、エリザベスカラーを巻いて物理的に噛めない状態にしたり、苦いスプレーなどをかけておいて噛まなくするという対処法を見かけますが、これは根本的な対策にならないうえ子犬のストレスを倍増してしまいかねないのでおすすめはしません。
※動物病院で治療のために出されたものでしたら医師の診断に従ってください。
子犬が人や自分の足を噛む~最後に

最後までお読みいただいて本当にありがとうございました。
子犬が人の足を噛む理由と対処法、子犬が自分の足を噛む理由と対処法についてご紹介してきました。
どちらもきちんとした対処を行ったほうが良いものだということをお分かりいただけたと思います。
ただ子犬が人の足を噛む場合は、噛まれた人がけがをしてしまう危険のほか、まとわりついてくる子犬を踏みつけてしまう危険もあります。
飼い主さんの足だけじゃなく、来客者の足を噛んでしまったら大変なことになりますし、早く人の足を噛んではいけないことを教えないと、人を噛むことが平気な犬に育ててしまう恐れもあります。
子犬の頃は足だったけど、成犬になったら届く範囲が広がるので噛まれる範囲も広がってしまい危険度が高くなってしまいます。
子犬の噛み癖を直し、なおかつ子犬と強い信頼関係を結べるしつけをできるだけ早く始めていただければと思います。
子犬をみんなに愛されるお利口さんな犬に育て、なおかつ子犬も人間社会で怖がらず、ストレスを感じずに幸せに生活させてあげるためにも、イヌバーシティを実践していただけることを願っています。